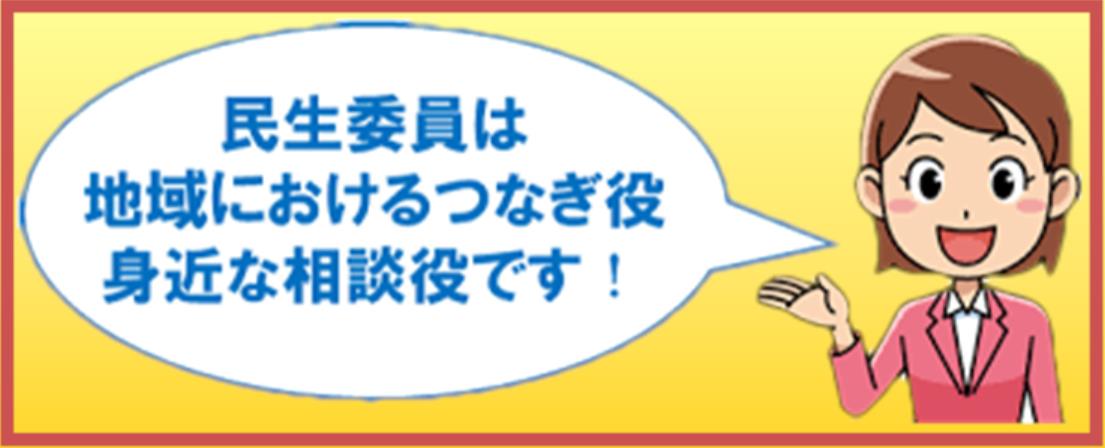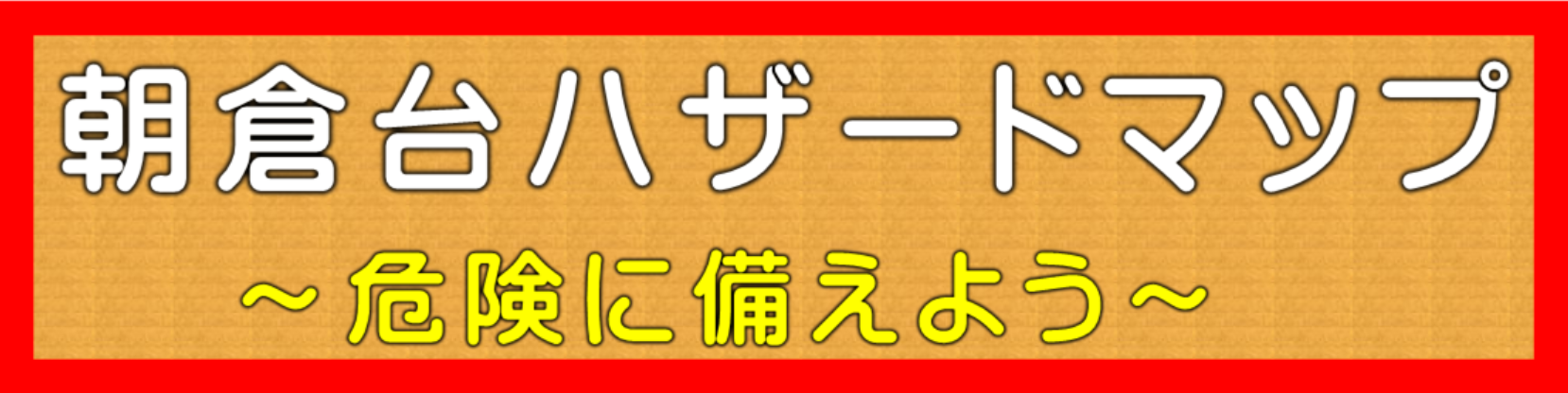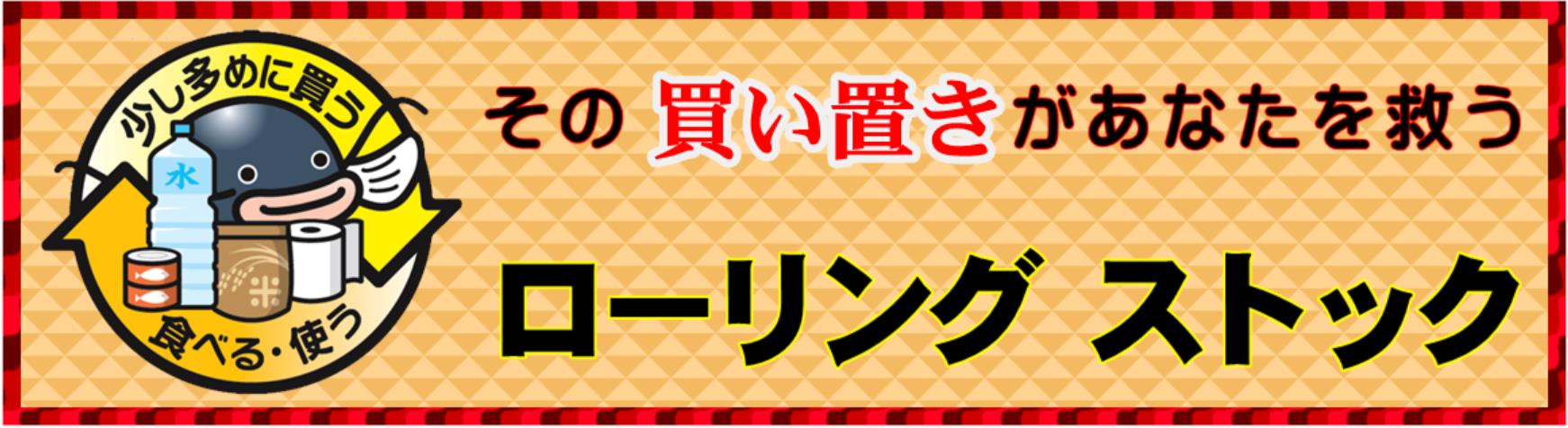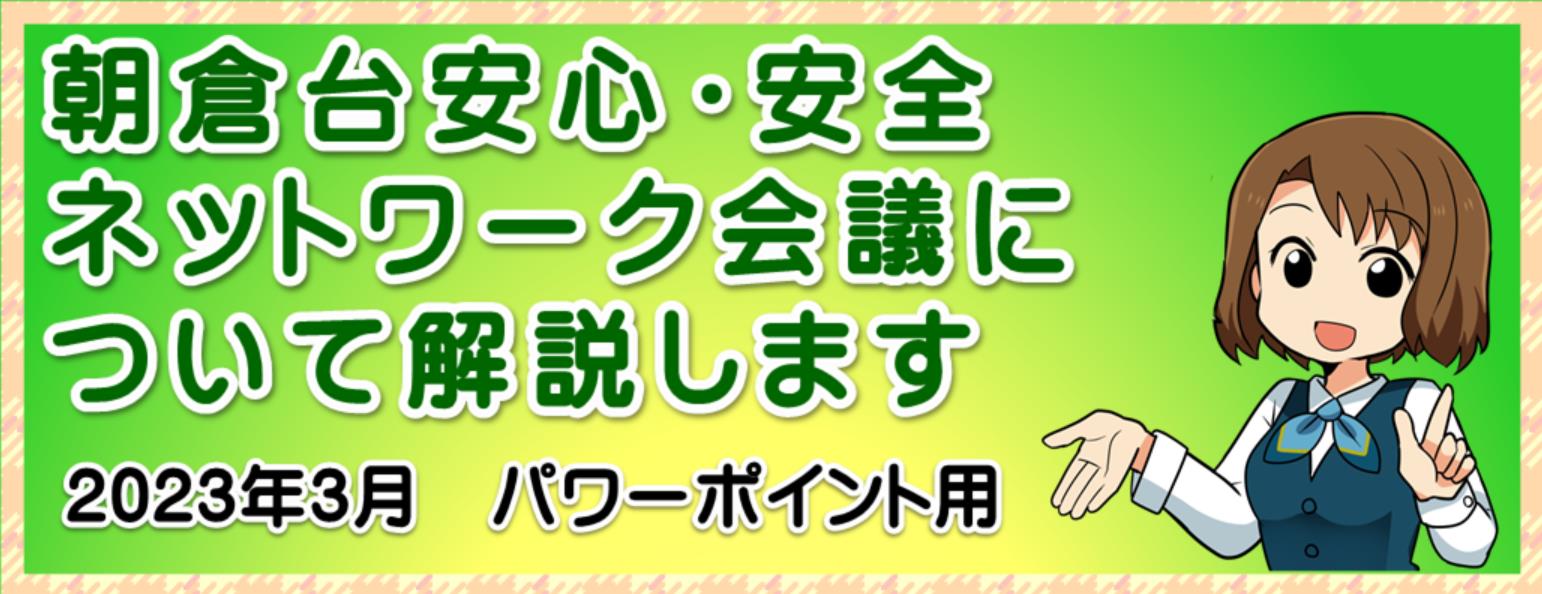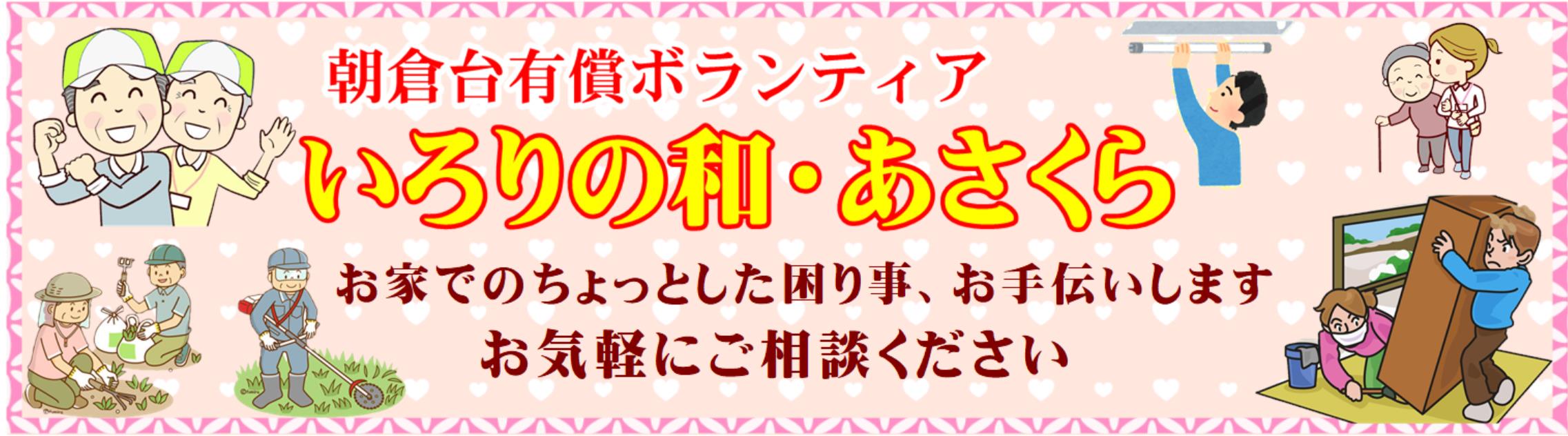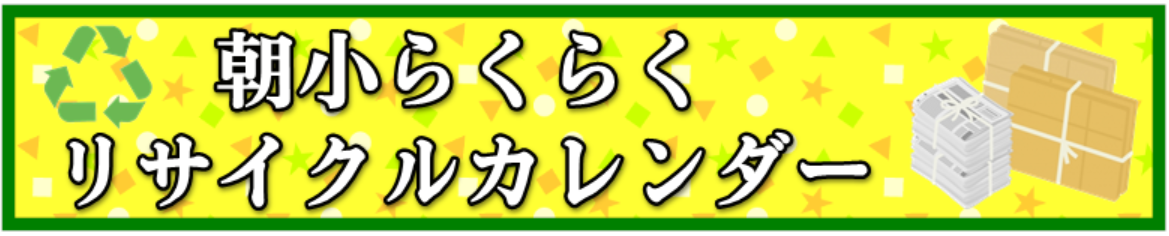桜井市観光ボランティアガイドの案内で万葉ゆかりの地、磐余の宮跡を訪ねました。
あいにくの小雨交じりの天候でしたが、ハイキング会のメンバー19名(男性10名女性9名)が参加、1班男性、2班女性に分かれて出発しました。
コースは、9時40分桜井駅南口を出発

若櫻神社(桜の井)

【観光メモ】櫻の井
「櫻の井」は第17代の覆中天皇(5世紀前半)がめでさせられた(感動した)清水で、桜井市発祥の地です。
井戸は、深さが九尺余り(約2.7m)で、直径が2尺2寸(約66cm)。
井水は、鏡のごとく澄み、特別の甘みがあり、水量豊かで、大和の七ッ井のひとつでした。
土舞台(芸能発祥の地)


【観光メモ】
土舞台は聖徳太子が初めて国立演劇研究所と国立劇場を設けた場所として伝わり、「日本芸能発祥の地」として顕彰されています。 この辺りは桜井公園として整備されていて春には桜が楽しめる。
阿部文珠院(西古墳)



【観光メモ】阿部文珠院(西古墳)
直径は約25メートルから30メートル、高さ約6メートル程度の円墳。内部には両袖式横穴式石室が設けられており、現在は南を向いて開口しています。
文殊院西古墳の築造時期は7世紀後半と推定されており、被葬者として、大化の改新後に左大臣となった阿倍内麻呂(安倍倉梯麻呂)の名が挙げられています。当地が古代の豪族・阿倍氏の勢力圏にあったこと、阿倍氏の氏寺として創建された安倍文殊院の境内に位置していることからも、阿倍内麻呂を被葬者とする説は確かに有力です。

【観光メモ】上之宮遺跡
「上之宮」の地名は聖徳太子が幼い時に過ごした宮殿・上宮にちなむという説があり、上之宮遺跡と聖徳太子との関連性を指摘する説もある。ただし『日本書紀』などの史書類には、現存していない磐余池のほとりに用明天皇の磐余池辺雙槻宮、その南隣に息子の聖徳太子の上宮があったとされており、磐余池の所在地が確定しない限り肯定も否定も出来ないとされる。また、阿倍氏など周辺地域を拠点に持つ豪族の邸宅である可能性もある。
等彌神社

【観光メモ】等彌神社
延喜式に記された由緒ある古社で、鳥見山の麓に鎮座する。創建の年月は明らかではないが、鳥見山の西麓を能登山ということから、「能登宮」とも言う。鳥居は、伊勢神宮内宮から譲り受けたもの。主祭神:上津尾社(本殿)天照大御神 祭神:下津尾社右殿(八幡社) 左殿(春日社)

社務所には1730年頃境内で発見されたと伝わる土偶のレプリカが販売されています。八咫烏とも云われていますが来歴は不明です。そういえばこの地は聖徳太子と縁の深い地で法隆寺の五重塔の中にもは虫類方の塑像が発見されています・・・

何か関係があるのかな・・・(;゚ロ゚)
魚市場跡

【観光メモ】魚市場跡
江戸時代でも桜井の中心地として桜井駅や桜井宿と呼ばれ、また江戸中期ごろから魚市場としても大変賑わった。毎月六回(二、七を定日とする)遠近の商人が商品を並べる六斎市の形で明治初年まで続けられた。特に「熊野鯖」を扱うことで人気があった。桜井市が材木の町と呼ばれる以前は魚市場の町であったことが石碑からもうかがえる。
ちなみに、桜井で魚市場と聞くと、連想する人物は、江戸日本橋の魚河岸(現在は豊洲の東京都中央卸売市場)発展に寄与した商人、大和屋助五郎です。
桜井出身の助五郎は、大坂夏の陣直後の1616(元和2)年までに江戸に出て魚問屋を開き、駿河から活鯛を生簀船で江戸に運ぶことに成功した人物で、漁師への前払金で産地独占的な魚河岸の流通機構を作り出した。

安田輿重郎生家
【観光メモ】安田輿重郎
評論家。奈良県生。東京帝国大学卒。大学在学中に同人誌『コギト』を創刊して文筆活動に入る。昭和10年亀井勝一郎らと雑誌『日本浪曼派』を創刊、民族主義と反近代主義を標榜して昭和10年代の指導的評論家になる。『日本の橋』『近代の終焉』『現代畸人伝』などがある。

こうして桜井駅南部付近をハイキングして12時30分桜井駅着の約5.5キロ3時間の行程を楽しみました。
解散後、全員桜井駅北口近くの台湾料理店で昼食を楽しみました。